ニコルソン・ベイカー『中二階』感想
ニコルソン・ベイカー 著/岸本佐知子 訳『中二階』(白水社)

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b205568.html
読み始め:2023/8/21 読み終わり:2023/8/23
あらすじ・概要中二階のオフィスへエスカレーターで戻る途中のサラリーマンがめぐらす超ミクロ的考察。靴紐が左右同時期に切れるのはなぜか。牛乳の容器が瓶からカートンに変わったときの素敵な衝撃。ミシン目を発明した人間への熱狂的賛辞等々、これまで誰も書こうとしなかった愉快ですごーく細かい小説。
読んだきっかけ
読んでいくぞ、とリストを作って三冊目。
コメント・感想
う、うるせ〜! しゃらくせぇ〜! いけすかねぇ〜! が第一の感想。とにかくうるさい。こいつと仲良くなれる気がしない。自分でつらつらと考えていることが本にされているのかな、と思ったが、作中に一連のテクストを語り手自身が「書いて」いることが仄めかされており、無理度が増した。気持ち悪いな……これを書く人間は気持ち悪いよ。ただしこれはあくまで、この小説の語り手がいけすかないというだけの話で、小説としては好奇心を刺激された。一人のビジネスマンが休憩に出てそれから戻ってくるまでだけに本一冊が費やされているのだが、よくもまあこんだけ細かいことを延々と書き続けていられるなと感嘆する。自分が普段なにげなく使っている製品や習慣などは、語られることのない多くの知恵に支えられており、しかもそれらはその製品が使われなくなったら誰にも受け継がれず忘れられていく。当たり前なのだが寂しい。この小説が、そんなあまねくプロダクトに向ける視線のバランスの良さには驚かされる。この小説に書かれた時代は紙製のストローからプラスチック製のストローに変化する過渡期だったらしく、語り手はプラスチック製ストローがコーラに「浮く」ことへの不満をこぼす。ちょうど私たちはプラスチック製ストローが紙製ストローに取って代わられることへの不満を口にしている世代で(私も紙製ストローが嫌いなうちの一人である)、まじで数十年で一周したんだなと感慨深い。そのほか、クソどうでもいい話にぐだぐだとページが割かれ続ける。脚注が長い。私は脚注がそんなに好きではなく、うっとうし〜と思ってしまう質ではあるが、本書の注釈は楽しかった。しかし(本書でまさに狙っているところである)本筋からどんどん脱線していくことへの気持ち悪さや不安というものがどうしても抜けず、読みながらイライラしていることのほうが多かった。この小説が私には合わないのではなく、意図的に「合わない」ように作られているとわかっているからこそ、馬鹿正直に最後まで読んでやったし、それなりの評価もできるのだが……、まあでも再読したいかと言われると全くしたくない。書影のエスカレーターに腰掛けた男が、ちょうど「そういう役者の独演会のポスター」みたいで、私そういうの好きじゃないのよね……となる。
終盤の周期律の話は面白かったし「殺してやりたい」とか「友人、自分には—がいない」とか、そういう部分でクスッとさせられる。出てくる小物や会話が全部絶妙なんだよな。これは私書けんな〜、人間が好きなひねくれ者しか書けない小説だ〜と圧倒された。私が人間が好き/嫌いなひねくれ者/ていない者のうちどれであるかは想像におまかせします。
また、時代的に仕方がないのだが、ゲイや同性愛者へのナチュラルな差別意識が投影されているので読むのには注意が必要です。
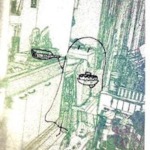
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.