サン=テグジュペリ『人間の土地』感想
サン=テグジュペリ著 堀口大學訳『人間の土地』(新潮文庫)
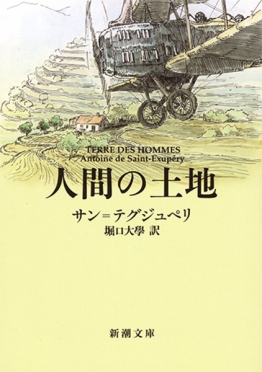
https://www.shinchosha.co.jp/book/212202/
読み始め:2023/4/6 読み終わり:2023/4/17
あらすじ・概要“我慢しろ……ぼくらが駆けつけてやる!……ぼくらのほうから駆けつけてやる! ぼくらこそは救援隊だ!”サハラ砂漠の真っ只中に不時着遭難し、渇きと疲労に打克って、三日後奇蹟的な生還を遂げたサン=テグジュペリの勇気の源泉とは……。職業飛行家としての劇的な体験をふまえながら、人間本然の姿を星々や地球のあいだに探し、現代人に生活と行動の指針を与える世紀の名著。
読んだきっかけ
星の王子さま以外も読んでおきたいな、というのと、飛行機の遭難に興味があったから。
コメント・感想
迫力が違う。めちゃくちゃ怖い。本物の荒野に出た小説家に勝てるわけない。後半には、実際に彼が僚友と遭難して砂漠で何日も水を飲めずに過ごし続けるところ、すんでのところで人を見つけ命を救われるさまを目撃することになるのだが、もうここはサスペンスとしても最高に面白くて、マジでこんなん勝てん、勝てんやろおい、と思わず笑ってしまう。文章がずっと良いな、これは確かにあの時代に空を飛んでいた人間にしか書けない。良かった文は、引用していくと全文になってしまうので、途中で付箋を貼るのをやめた。すごいものを読んだ。星の王子さまもすごいけど、こっちのほうが好きだな。
良かった文・シーン
・ぼくら人間について、大地が、万巻の書より多くを教える。理由は、大地が人間に抵抗するがためだ。人間というのは、障害物に対して戦う場合に、はじめて実力を発揮するものなのだ。もっとも障害物を征服するには、人間に、道具が必要だ。人間には、鉋が必要だったり、鋤が必要だったりする。農夫は、耕作しているあいだに、いつかすこしずつ自然の秘密を探っている結果になるのだが、こうして引き出したものであればこそ、はじめてその真実その本然が、世界共通のものたりうるわけだ。これと同じように、定期航空の道具、飛行機が、人間を昔からのあらゆる未解決問題の解決に参加させる結果になる。
(p.7-8)
ぼくは、アルゼンチンにおける自分の最初の夜間飛行の晩の景観を、いま目のあたりに見る心地がする。それは、星かげのように、平野のそこここに、ともしびばかりが輝く暗夜だった。
あのともしびの一つ一つは、見わたすかぎり一面の闇の大海原の中にも、なお人間の心という奇蹟が存在することを示していた。あの一軒では、読書したり、思索したり、打明け話をしたり、この一軒では、空間の計測を試みたり、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭したりしているかもしれなかった。また、かしこの家で、人は愛しているかもしれなかった。それぞれの糧を求めて、それらのともしびは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っていた。中には、詩人の、教師の、大工さんのともしびと思しい、いともつつましやかなのも認められた。しかしまた他方、これらの生きた星々のあいだにまじって、閉ざされた窓々、消えた星々、眠る人々がなんとおびただしく存在することだろう……。
努めなければならないのは、自分を完成することだ。試みなければならないのは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っているあのともしびたちと、心を通じあうことだ。
・老サラリーマンよ、現在のぼくの僚友よ、ついに何ものもきみを解放してはくれなかったが、それはきみの罪ではなかったのだ、きみは、かの白蟻たちがするように、光明へのあらゆる出口をセメントでむやみにふさぐことによって、きみの平和を建設してきた。きみは、自分のブルジョア流の安全感のうちに、自分の習慣のうちに、自分の田舎暮しの息づまりそうな儀礼のうちに、体を小さくまるめてもぐりこんでしまったのだ、きみは、風に対して、潮に対して、星に対して、このつつましやかな堡塁を築いてしまったのだ。きみは人世の大問題などに関心をもとうとはしない。きみは人間としての煩悩を忘れるだけにさえ、大難儀をしてきたのだ。きみは漂流する遊星の住民などではありはしない。きみは答えのないような疑問を自分に向けたりはけっしてしない。要するにきみは、トゥールーズの小市民なのだ。何ものも、きみの肩を鷲掴みにしてくれるものはなかったのだ、手遅れとなる以前に、いまでは、きみが作られている粘土はかわいて、固くなってしまっていて、今後、何ものも、最初きみのうちに宿っていたかもしれない、眠れる音楽家を、詩人を、あるいはまた天文学者を、目ざめさせることは、はや絶対にできなくなってしまった。
(p.24-25)
・ところが、ぼくらの視力は磨ぎすまされ、ぼくらは無残な進歩をとげた。飛行機のおかげで、ぼくらは直線を知った。離陸すると同時に、ぼくらは、水飼場から家畜小屋へと行きたがったり、町から町へと練り歩きたがったりする道路を捨てる。昔なつかしい奴隷の身分をかなぐり捨て、泉を追いかける必要から解放され、ぼくらは遠い自分たちの目標に、ぴたりと機首を向ける。するとはじめて、ぼくらの直線的な弾道のはるかな高さからぼくらは発見する、地表の大部分が、岩石の、砂原の、塩の集積であって、そこにときおり生命が、廃墟の中に生え残るわずかな苔の程度に、ぽつりぽつりと、花を咲かせているにすぎない事実を。
(p.73−74)
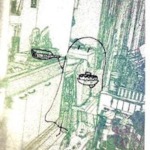
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.