冲方丁『天地明察 上』感想
冲方丁『天地明察 上』(角川文庫)

https://www.kadokawa.co.jp/product/201108000099/
読み始め:2023/2/23 読み終わり:2023/2/23
あらすじ・概要徳川四代将軍家綱の治世、ある「プロジェクト」が立ちあがる。即ち、日本独自の暦を作り上げること。当時使われていた暦・宣明暦は正確さを失い、ずれが生じ始めていた。改暦の実行者として選ばれたのは渋川春海。碁打ちの名門に生まれた春海は己の境遇に飽き、算術に生き甲斐を見出していた。彼と「天」との壮絶な勝負が今、幕開く——。日本文化を変えた大計画をみずみずしくも重厚に描いた傑作時代小説。第7回本屋大賞受賞作。
読んだきっかけ
本屋大賞のノミネート作品全部読む、を実行中。図書館で目についた。
コメント・感想
これに追いつく、そして追いこせるような小説が書けるんか……? とにかくすごい作品。時代小説を全く読んだことがないため、最初誰が実在していてどこからが創作なのか(つまり時代小説を読む上での作法が)よく分からなかったが、そうした状態で読めてむしろよかったと思った。旅先の電車でのめり込んだ。終始鳴り続ける「からん、ころん」という勝負の音、そして太陽と月の交錯であり、驚嘆したときに自ずと発される柏手の音……と、印象的な音の繰り返しが効果的に多用される。前半ではからん、ころんは二回登場、柏手も二回。二回目の柏手は上巻の終わりに配置されていて、すごく爽やかな味があって、良い締め方だなと思う。
託す、託されるというテーマが「第三章 北極出地」で提示される。他にもテーマは無数にあるが(一人の人間の生涯を描くのだから当然だけど)、そのなかでは「天才の孤独」「天才が別の天才に向ける感情」などの描かれ方も興味深かった。でもやはり主たるテーマは「託されること」。これは、春海は生涯人を看取ることが多かった、という旨の記載(そして史実)にも表れているし、観測隊の建部と伊藤両人から春海はそれぞれ大願を託されている。
上巻を読むうちは、正直、「算術と暦術が繋がるのはわかるけど、囲碁と何が繋がるんだ?」と思っていたが、下巻でそれも解消されよかった。もとより、春海は御城碁(予め勝負がついた譜を将軍の前で再現して打つ)に飽きており、囲碁の天才であるところの道策にも同様の貪欲さがある(しかしこちらは囲碁に夢中で、春海が星や算術に現を抜かしていることを快く思っていない)という対比はあるのだが、それだけでは繋がりが薄いなと思っていたので、下巻はそこも楽しみだった。
うーん困った、良い作品ほど感想がうまく出てこない。私が言うことはもうないと思ってしまう。春海はそれでも関孝和に食らいついたし、私もそうするべきなのだが。よくこれだけのものを調べ上げたな……と敬服する。本書に書き込まれている史実や知識、背景の説明、人物や役職の説明などだけでも相当な量なのだが、これだけのものを書き上げるには書き込まれている量の百倍以上は調べた事実があるのだろうと推察する。まじですごい。あと、これはプロットの分解をしていて気づいたことだが、上巻と下巻でページ数がまるきり同じなのもすごいを通り越して気味が悪い。偶然であってほしいが、なんとなく人為的なものであるように思う。
良かった文・シーン
・ぱーん、と鋭い音が鳴った。無意識に、稿本に向かって、柏手を打っていた。
(p.135-136)
何の必然もない、奇妙ともいえる行為だったが、それが幼時からの春海の心身に染みついた信仰であり作法だった。心の異変において仏徒の一派が南無阿弥陀仏を唱えるように、切支丹が思わず手で十字を切るように、この咄嗟のときに、それが出た。
神道はその作法の古伝が失われて久しい宗教である。何のための柏手か、何のための拝礼か、それらの行為によって何が得られるのか、そうした教義がない。だが昨今は、優れた神道家たちにより、神道独自の宇宙観から新たに意味が解釈され、急速に体系化されようとしていた。
左手は火足すなわち陽にして霊。
右手は水極すなわち陰にして身。
柏手とは、陰陽の調和、太陽と月の交錯、霊と肉体の一体化を意味し、火と水が交わり火水となる。柏手は身たる右手を下げ、霊たる左手へと打つ。己の根本原理を霊主に定め、身従う。このとき火水は神に通じ神性開顕となって神意が降りる。
手を鋭く打ち鳴らす音は天地開闢の音霊、無に宇宙が生まれる音である。それは天照大御神の再臨たる天磐戸開きの音に通じる。
柏手をもって祈念するとき、そこに天地が開く。そして磐戸が開き、光明が溢れ出る。
光明とは、いわば種々に矛盾した心が、一つとなって発する輝きである。その輝きは身分の貴賤を問わず、老若男女を問わない。
恐れや迷いを祓い、真に求めるものを己自身に知らしめ、精神潔白となる。春海は、二度、三度と柏手を打った。伊勢神宮では八度の柏手たる八開手、出雲大社では四拍手の作法。だがこのときの春海には三度で足りた。
自分は今、神事の中にあるという昂揚が湧いた。それを勇気にして稿本を開いた。
読んだ。たちまち柏手の光明とは異なる輝きが来た。さながら草原に稲妻の群れを見るような、知性の閃きの連続だった。強烈な驚きに打たれたが、怖さは感じなかった。薄明かりのせいで咄嗟に字の判別がつかないところがあって、それが怖さを麻痺させてくれた。
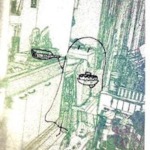
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.