井上彼方編『京都SFアンソロジー』感想
井上彼方編『京都SFアンソロジー ここに浮かぶ景色』(社会評論社)

読み始め:2023/8/23 読み終わり:2023/8/23
あらすじ・概要京都にゆかりのある8名の作家が綴る、京都SFアンソロジー。1000年の都? いえいえ、わたしたちの棲む町。アート、池、記憶、軒先駐車、松ぼっくり、物語――。妖怪もお寺も出てこない、観光地の向こう側をお届けします。大阪/京都を拠点にするKaguya Booksより、待望の地域SFアンソロジー第1弾刊行!
読んだきっかけ
予約しており先日届いたので。
コメント・感想
個々の作品はもちろんなのだが、後書きが非常に良かった。「記憶」や「過去の蓄積」がテーマになっているものばかりだなというのは読み途中にも感じたことで、編者の方でもそれを意図して掲載順を決めていたのがわかってしっくりきた。
千葉集「京都は存在しない」。新島のギラギラした感じが良い。ずっとはらはらとするやりとりが続く。こんなのも書けるのか……と作者の引き出しの広さに驚いた。私たちが確かに知っているはずの「京都駅」や「京都タワー」がこの世界では創作の産物である(でも実際に視えた人もいる)という設定が面白い。イノダコーヒーの細かい話が面白い(行ったことないんですけどいつか行ってみたいんですよね)。終わり方も良かった。あっさりした終わり方が好きなので。「ありがとね」って言ったか言ってないかわからないのも、新島の何か抱えてそうな底の知れなさが最後まで明かされずに終わるところも好き。あと、細かいけど対談相手からインタビュー相手になった、って部分に悶えそうになった。こういう細かいところが本当に上手いなと思う……。
暴力と破滅の運び手「ピアニスト」。面白かった。これを機にレベッカ・クラークの「ヴィオラとピアノのためのソナタ」を聴いてみた。確かに警笛のようなヴィオラから始まっていた。音楽を小説に表現するのって難しくて、大抵は大げさな比喩に陥りがちだと思うのだが、運び手さんは音楽の知識も持ち合わせた方なので音楽の展開に合わせた言葉選びがきちんとなされていて、いいなーと思った。それに、音楽で何か視覚的な描写が立ち現れることを〈仮相〉というギミックを取り入れることで自然に作品のなかで提示していて、テクいぜ〜となった。それだけではなく、「時間を凍らせる」というイメージが主要登場人物から提示されるのが美しかった。あと、碓氷来てるけど大丈夫か? というところで終わってしまうのが憎い。でも、語り手の言うように「何も問題はない」のだろう、きっと。
鈴木無音「聖地と呼ばれる町で」。この小説自体が一本の映画みたいだ。景色が美しい。ニンアリと暮らす、という作中作のタイトルもいいなと思った。美しい景色のなかにけっこう揺さぶられる言葉があって、ぎくりとする。場所を書くことの有毒性を真正面から描いている。答えは出ない。どうすればいいのだろう。極めつきは「スランプからの脱却は祝福されるべきであるという既存の物語」という文字列。強火すぎて焼かれそう。映画内で、小説内で描かれたこと以外にも世界がある。このあたり「京都は存在しない」とも接続してくるなと思う。
野咲タラ「おしゃべりな池」。池の調査をされていたのはこれだったか、というのがまず(どちらが先かはわからないが)。面白かった。入りが素晴らしい。「こりゃたいそうなレンコン畑じゃな」という発言、あまりにも良い。シャボン玉を飛ばすカワウソというのが魅力的で、このカワウソが関わってくるオチもよかった。てか池、本当におしゃべりだな。蓮の花を流れ星だかなんだかのように「アッ」と見つけるシーンがよかった。池の言霊が出なくなっても、つい池について喋ってしまう(喋らされてしまう)のが微笑ましい。
溝渕久美子「第二回京都西陣エクストリーム軒先駐車大会」。これ読み終えてから冒頭読み返すとガラッと印象が変わる。「早よクルマどけて。邪魔や!」このセリフ、本当に真剣に言ってるんだと思うけどこの大会の置かれた状況を考えると途端に感慨深いセリフになって良い。綿谷の「いそう」感が良かった。あと、コツをおじいちゃんに聞きに行くくだりが、あるかないかで言うとギリありそうだよなという絶妙なラインで面白かった。着眼点がまず面白いし(私は免許を持っていないが絶対に京都に車なんか停めたくない)、行政が無能すぎるところもおかしくて寂しい(笑っている場合ではないが)。
麦原遼「立看の儀」。最後まで世界がどのようになっているのか説明されなくて、その余白で我々は感じるしかないのだが、「資料汚染期」「区分」「冷凍睡眠」とどことなく不穏な用語が飛び交う。「あなたは、私がすることを、推し進めるべきだと、進言しないで」という先輩のセリフも意味深だ。童子像による時計台占拠の再現が儀礼として後世に残されているというのが皮肉だし、最後に先輩が放った火花が眩しい。守らなければ消えてしまうが理念ごとそれを再現し続けるのは難しい。きっとこれからも立看の儀は続いていくのだろう、何事もなかったかのように。
藤田雅矢「シダーローズの時間」。美しかった。おばあちゃんとの仲の良さも羨ましくなる。京都府立植物園は、素晴らしい。だがこの場所を舞台にした小説は初めて読んだことに気づいて、嬉しかった。シダーローズという着眼点が見事だし、そこからフィボナッチ数列、宇宙へと思考が変遷していく跳躍は読んでいて気持ちが良かった。主人公の人生には京都府立植物園が身近にあり、年を経るごとにその付き合い方は変わっていく。あるときは昔の植物園を幻視し、あるときはヒマラヤ杉の童と遭遇し、あるときはその先に宇宙を見る。希望の持てる温かい物語で、終盤にふさわしい作品だった。
織戸久貴「春と灰」。世界観が膨大で、文字通り「つづく」のではないかと思わされる作品。アニメの第一話だった。球体関節人形たちが無人の街を防衛しているというのも、図書館から動力源を得ているという設定もよかった。あと、〈移動図書館〉はカッコ良すぎるのでずるいのではないか。終わり方がアンソロジーの終わり方として美しすぎる。これは、主人公の過去の記憶なのか、それとも未来の記憶なのか、どちらにせよ「在ってほしいひととき」だ。
「(前略)そもそも個々の物語は一般化を拒むものだからだ。だから私たちは物語を作り続けるし、読み続ける。」
良いアンソロジーだった。
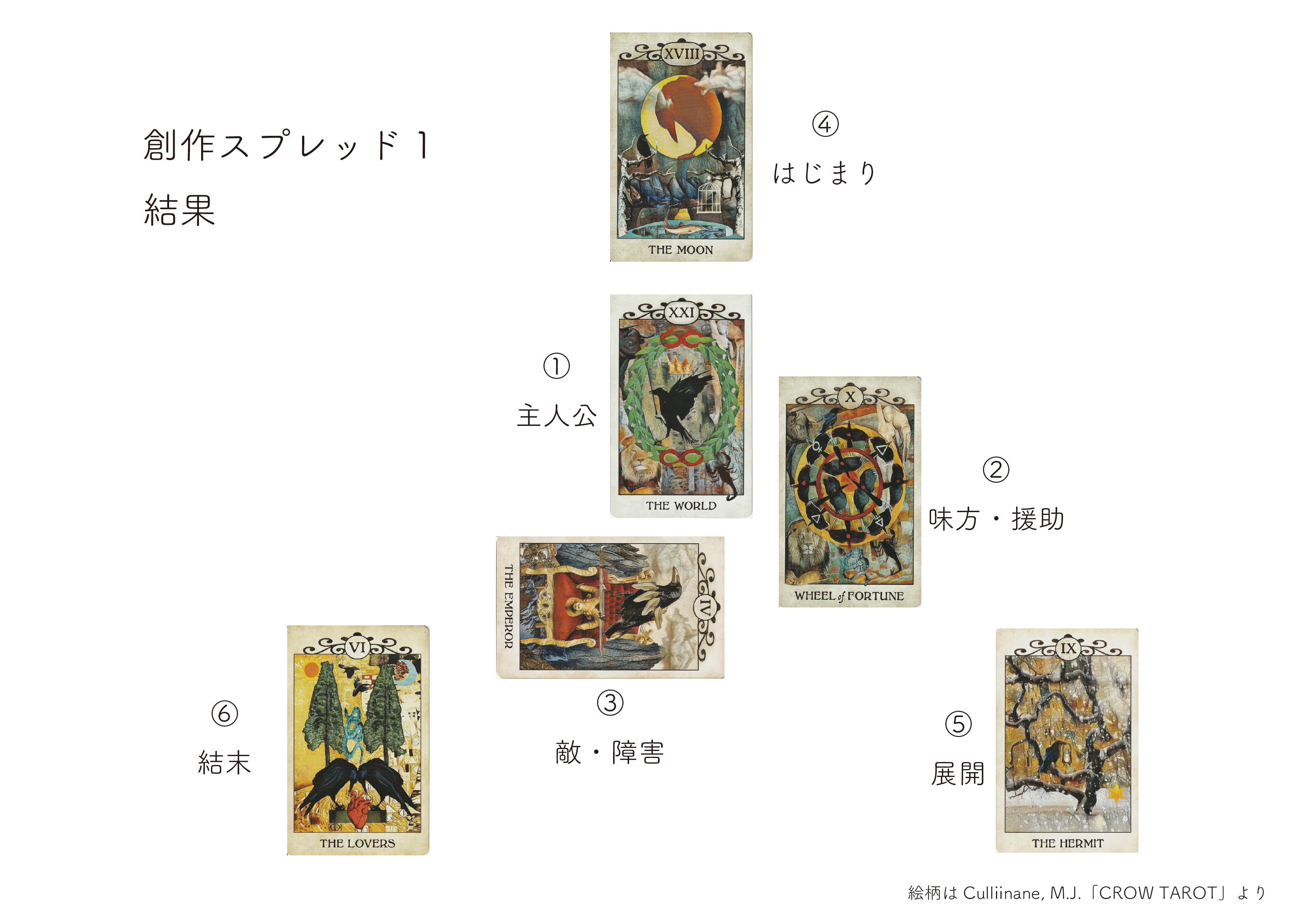
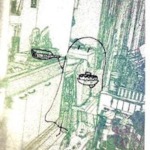
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.