フェローチェ
彼女が笑うと、部屋の中の気圧が少しだけ下がるような気がする。彼女というのはハーピーで、三ヶ月前から同居している。ハーピーにも当然名前はあり、彼女はフェリクス・エクスエクス・バジリーナといった。フェリクス・エクスエクス・バジリーナ(愛を込めてフェローチェと呼ぼう)は、孔雀の羽を持つハーピーだ。フェローチェとの出会いは一瞬。神社でお参りしようと鐘を鳴らすと、天井から落ちてきた。
「なんと雑多な。この国のおおらかさの帰結。面妖なり」
私はハーピーを連れ帰った。もちろん落下してきたフェローチェは初めしかめ面をしていたが、コンビニでスティック状のチキンを買ってやると無我夢中で貪り始めた。
「上半身がヒトなのであるから同類食らいにはならないというわけ」
そのハーピーから名前を聞き出すのには苦労した。なにせ一週間は唸ることしかしなかったもので、彼女には最初言葉がないのだと思い込んでいた。それを、私がローリエをたっぷりと浮かべたポトフを作っている最中、彼女はぽつりと漏らしたのだった。
「フェリクス・エクスエクス・バジリーナは、おまえの世話になることにしよう」
もちろん私ははなからそのつもりだったので、フェローチェにもポトフをそそいでやり、猫舌であることを見越してスプーンの上で溶けたじゃがいもを冷ましてやった。フェローチェは好き嫌いをせずなんでも食べた。孔雀の羽は彼女が感極まるときに広げられた。フェローチェは女性であるはずだったが、雄の孔雀の羽を備えていた。
フェローチェはラジオが好きだった。私としてはなんとはなしに捻りをつまんでみただけだったが、彼女はそれ以来ラジオにぞっこんだった。音が平面から発せられることを不思議がった。箱から同心円上に音の波がゆたゆたと彼女の耳に届くとき、彼女は美しい羽を震わせた。私の勤めていた会社の上司がラジオのパーソナリティーを務めていて私は顔をしかめた。ラジオ会社で働いていたわけではない。ただ、その上司がなんでもできただけだ。上司はクマバチのように言葉の波を乗りこなした。フェローチェは特にその上司の語りを気に入ったというわけでもなさそうだったが、それでも上司の声を聞くことが彼女の日課となった。フェローチェは上司のラジオを聴いているとき、よく声を上げて笑った。決して可憐な笑い声ではなく、どちらかといえば白雪姫を陥れんとする魔女がけたたましく上げるような金切り声で、しかしその後、sighという言葉でしか表現できないような切なげな息を漏らした。その息が漏れると、部屋の気圧が1hPa下がる。我が家の気圧計は、既に使い物にならなくなっていた。
五苓散という漢方薬があり、これは低気圧によって誘発される体調不良に効果があると考えられている。私は近所の薬売りのもとを訪ねて五苓散を麻袋一杯に処方してもらった。これで、彼女といつまでもいようと思った。帰宅すると、フェローチェは床にぺたりと座り込んで所在なさげにこちらを見てきた。ラジオは全国の交通情報を流していた。国道三号線の上りに深刻な渋滞が発生。フェローチェには道というものがわかるのだろうか。私は彼女をdriveに連れていくべきだろうか。
「手、見せて」
私はフェローチェの手の甲にハンドクリームを塗ってやった。彼女の手は冷たかった。無機質な感じがして好ましかった。フェローチェはハンドクリームの香料が気に入らなかったのか顔をしかめたが、その手に潤いが戻り始めると満足げに喉を鳴らした。フェローチェが水道代の督促状を差し出すので、私はそれをびりびりに破いて捨てた。仕事はいずれ見つけるはずだった。電気もガスも止まってからは、私はフェローチェとぴったりとくっついて眠ることが増えていた。フェローチェが私のことをどう思っているのかはわからなかった。
私がフェローチェを愛しているのに、特段深い理由はない。フェローチェは刺繍をした。
「バジリスクをいじめていたときさ、こうしてあいつの一番嫌いな模様を皮膚に縫い込んでやったものだよ」
彼女が最終的にバジリスクに敗北してこの地にやってきたことを私はうすうす予感していたが、私は何も言わなかった。そうして私のブラウスは彼女の施す刺繍だらけになり、なかなか不可思議な模様で満たされていた。フェローチェは黒い糸しか使わなかったので、私の生成り色だったブラウスはだんだんと真っ黒に染まっていった。フェローチェが縫い込んでくれたブラウスを着て、土葬のアルバイトに行った。穴を掘って埋めるだけなので簡単だったし、水道代を払うことができたので良かった。春になるころには、電気もガスも元通りになり、私は土を掘って死体を埋めて、フェローチェの元へと帰り、フェローチェとラジオを聴く。生活はうららかに過ぎていった。
フェローチェのために軽を借りた。山の方へdriveをするのだ。フェローチェを久々に外へと連れ出した。助手席に座ってもらったが、念のためトイレシートを座席に敷いた。安全のためにシートベルトをしてもらいたかったが、極度に嫌がったので、そのまま発進した。ラジオを流すとまた上司が流暢に私の知らない文法を話しており、フェローチェはそれを聞いてギャハハと笑った。車の気圧が1hPaずつ下がっていった。
私は五苓散を何度も飲んだ。途中、マクドナルドに寄ったので、フェローチェの下半身を毛布でくるんだ。私はフィッシュフィレオを頼み、フェローチェは侍マックを食べた。ドライブスルーで注文するときに、窓を開けたら空気がぶわっと入ってきた。かなり気圧が下がっていたらしい。店員はフェローチェがヒトではないことに特に気づかない様子で、「明日の山は凍りますね。ばいちゃら」と言った。
車は山道を蛇行した。フェローチェは妙にごきげんで、ゲラゲラと笑っていた。風船が風船であることを自覚したときみたいな笑い声だった。段々と山の天気が怪しくなってきて、フェローチェが笑うたびに大粒の雹が落ちてきた。フェローチェにカルスト台地を見せてやりたくて、山を上へ上へと進むのだが、フェローチェの笑い声はどんどん甲高くなっていって、呼吸は荒く、笑いの合間に存在している生物のようになって、車の気圧はさらに下がっていき、それに呼応して山の天気もどんどん具合が悪くなっていって、私は絶好の土葬日和だと思った。羊の群れのように連なる岩々の隙間を縫って緑がやけに明るく生い茂っている。風は強く、ついには嵐となって、氷のつぶてと雷が呼応して、黒々と降りてきた空は深海と見紛うほどで、私はついに車を止めて、フェローチェとともに外へと一歩踏み出した。
フェローチェが羽を大きく広げたので、飛ばされそうになる。私はぐっとフェローチェの手を握りしめた。フェローチェはずっと笑っていて、その声は天まで轟いて、風はごうごうと勢いをまし、私の黒のブラウスからは刺繍の糸が解け始めて、私たちはついに宙へ浮いた。私は糸を解き放ちながらフェローチェとともに上昇し、フェローチェはずんずん笑って天へと突き進んでいく。レンタルした軽は横転して、もう私の力では元に戻せそうになかった。私たちは天へと吸い込まれていき、フェローチェは笑うことをやめない。甲高く、不吉な声がこうも楽しげで愛おしい。私はフェローチェのもう片方の手も探り当てて、私たちは黒い糸と孔雀の羽を撒き散らしながらくるくると上昇していった。眼下には沈黙した羊たちの群れが見えた。誰も彼もが空を見上げていた。いかずちよりも鋭く、たつまきよりも豪快に、彼女は笑った。
突然視界が開けた。
私たちは、空と宇宙の境目にいて、フェローチェは突然笑うのをやめた。フェローチェは私を一瞥した。私はもうすぐ糸無しになるところだった。
「あはは」
今までに聞いたことのない可愛らしい声で、彼女がはにかんだ。私の願いは通じたのだ。
神楽が聞こえた。私は神楽ののたりとした低音に合わせて揺蕩って、フェローチェは孔雀の羽を全開にして静止した。太陽が下から突き上げてきた。私はフェローチェのことを抱きしめたくなった。私はフェローチェの懐に飛び込んだ。フェローチェは私の身体を抱きとめて、ゆっくりと服を脱がせた。私は羽毛の暖かさにうずもれて、フェローチェの腕に抱き取られて、上昇した。私は寒かったが、それはフェローチェの温かさがあってのことだった。フェローチェが私を取りこぼさないようにしてくれるのが嬉しかった。雷が鼓として機能して、その音と呼応してフェローチェが私を貪った。私の体内を構成する気圧がどんどん下がっていった。最後の黒い糸が、私の身体から滑り降りていって、下へ下へと落ちていった。
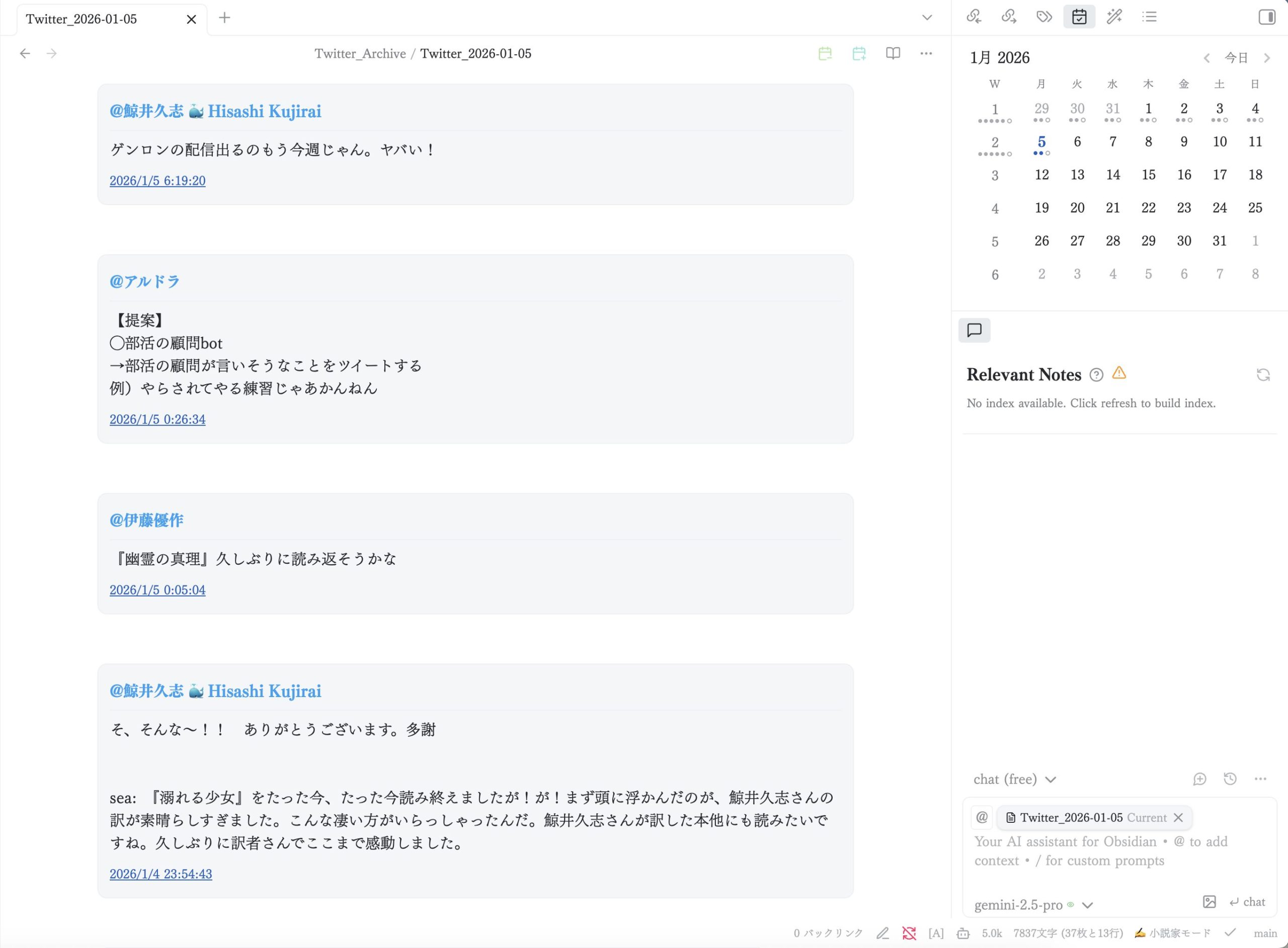


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.